歯茎からの出血・口臭が気になる!
どのような時に受診すべきか
歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどないことが多いですが、以下のような症状が現れたら歯科医院への受診をお勧めします:
- 歯磨きの際に歯茎から出血する
- 歯茎が赤く腫れている
- 口臭が気になる
- 歯がグラつく感じがある
- 歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなった
- 歯が長くなったように見える(歯肉退縮)
- 噛むと痛みを感じる
- 歯茎から膿が出る
症状がなくても、定期的な検診(6ヶ月に1回程度)を受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。歯周病は進行すると歯を支える骨が溶けてしまい、最終的には歯を失う原因となりますので、早めの受診が大切です。
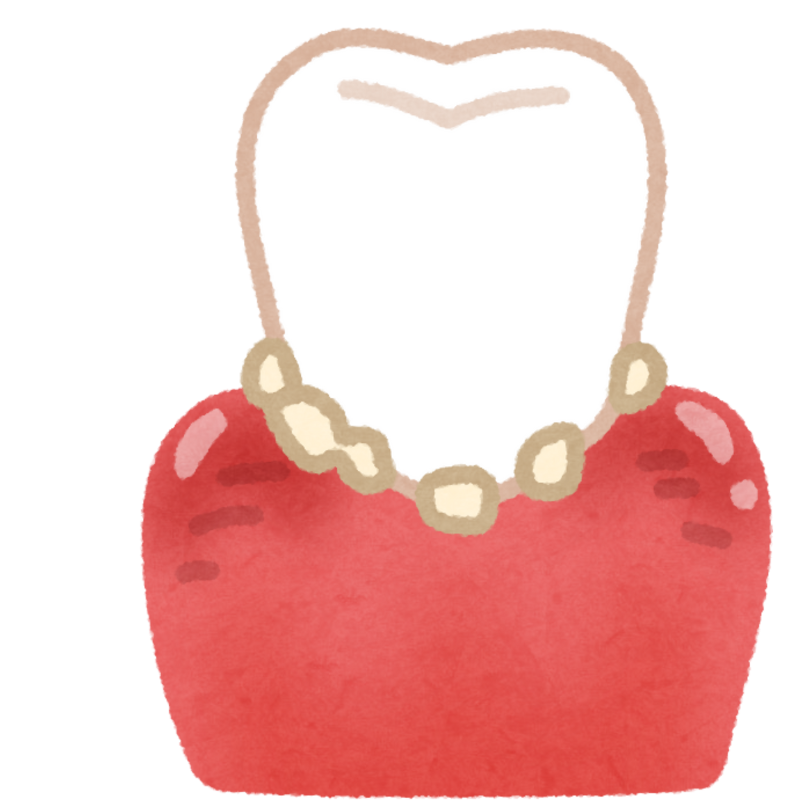
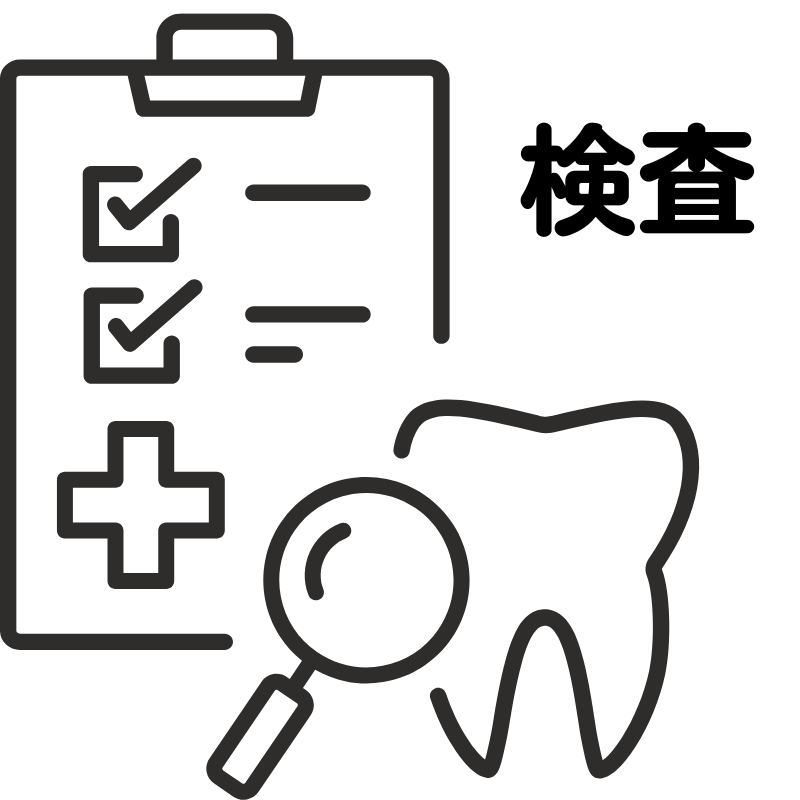
来院時の検査
- 問診
まず、患者さんの全身の健康状態や生活習慣、歯科的な悩みについて詳しくお聞きします。喫煙習慣や全身疾患(糖尿病など)は歯周病と関連性が高いため、正確にお伝えください。
- 口腔内検査
- 視診と触診: 歯茎の状態、腫れ、色の変化などを確認します
- プロービング検査: 専用の器具で歯と歯茎の間の溝(歯周ポケット)の深さを測定します。健康な状態では1〜3mm程度ですが、歯周病が進行すると深くなります
- 動揺度検査: 歯のグラつきの程度を確認します
- 出血の有無: 歯周ポケットの検査時に出血があるかどうかを確認します
- 咬合検査: 噛み合わせに問題がないか確認します
- レントゲン検査
- デンタルX線: 個々の歯の状態や歯槽骨(歯を支える骨)の状態を確認します
- パノラマX線: お口全体の状態を一度に確認できる検査です
- CT検査
必要に応じて歯科用CTによる検査を行います。CTは通常のレントゲンでは見えない3次元的な情報を提供し、以下のメリットがあります:
- 歯を支える骨の状態を立体的に把握できる
- 歯周ポケットの深さと骨の吸収状態の関係が明確になる
- 根分岐部病変(複数の根を持つ歯の分岐部分の病変)の正確な診断が可能
- 治療計画の立案に役立つ詳細な情報が得られる
CT検査は放射線被曝を伴いますが、歯科用CTは医科用CTと比較して被曝量が少なく設計されており、必要な場合には大変有用な検査です。
治療計画
検査結果に基づいて、あなたの歯周病の進行度を判断し、個別の治療計画を立てます。一般的に歯周病の進行度は以下のように分類されます:
- 歯肉炎: 歯肉のみの炎症で、適切なケアで完全に回復可能
- 軽度歯周炎: 歯を支える骨にわずかな吸収が見られる
- 中等度歯周炎: 歯を支える骨の吸収がやや進行
- 重度歯周炎: 歯を支える骨の吸収が著しく進行
治療計画は、症状の程度、全身状態、生活状況などを考慮して立案します。通常、次のようなステップで進めていきます:
- 応急処置:痛みや急性炎症がある場合はまずその対処
- 歯周基本治療:プラークコントロール指導、スケーリング・ルートプレーニングなど
- 再評価:基本治療の効果を評価
- 歯周外科治療:必要に応じて実施
- メインテナンス:定期的な検診とケア
治療期間は症状の重さや患者さんの協力度によって異なりますが、基本治療だけでも数ヶ月かかることがあります。
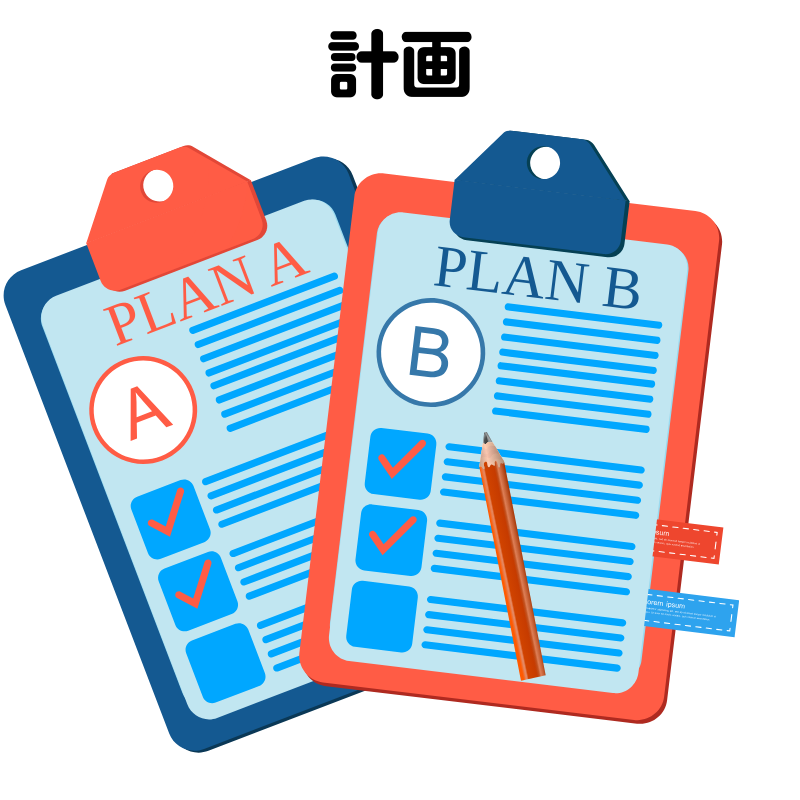

治療
- 歯周基本治療
プラークコントロール(セルフケア指導)
- 正しい歯磨き方法の指導
- 歯間ブラシやフロスなどの補助的清掃用具の使用方法指導
- 生活習慣の改善アドバイス(禁煙指導など)
専門的機械的歯面清掃(PMTC)
歯科医師や歯科衛生士による専門的な歯の清掃を行います。
スケーリング・ルートプレーニング
- スケーリング:歯の表面や歯肉縁下の歯石(プラークが石灰化したもの)を除去します
- ルートプレーニング:歯の根の表面をなめらかにし、細菌の付着を防ぎます
必要に応じて局所麻酔を使用することもあります。症状が重い場合は複数回に分けて実施します。
- 再評価
基本治療終了後、約1〜2ヶ月後に歯周ポケットの深さや出血の有無などを再検査し、治療効果を評価します。多くの場合、この基本治療で症状は改善しますが、改善が不十分な部位がある場合は次のステップに進みます。
- 歯周外科治療(必要な場合)
再評価の結果、以下のような場合に歯周外科治療を検討します:
- 歯周ポケットが依然として深い(5mm以上)
- 複雑な形状の骨欠損がある
- 根分岐部病変がある
主な歯周外科治療には以下のものがあります:
フラップ手術
歯肉を一時的にめくり上げ、歯根面の清掃や骨の形態修正を行います。
歯周組織再生療法
特殊な材料(メンブレンやエムドゲインなど)を用いて、失われた歯周組織の再生を促します。
歯肉移植術
退縮した歯肉を回復させるための手術です。
経過観察
治療後は定期的な経過観察を行い、症状の安定を確認します。通常、治療後3〜6ヶ月は比較的短い間隔で来院していただき、状態が安定したと判断されればメインテナンスに移行します。
経過観察では以下を確認します:
- 歯周ポケットの深さ
- 出血や排膿の有無
- 歯の動揺度
- プラークコントロールの状態
- 必要に応じてレントゲン検査

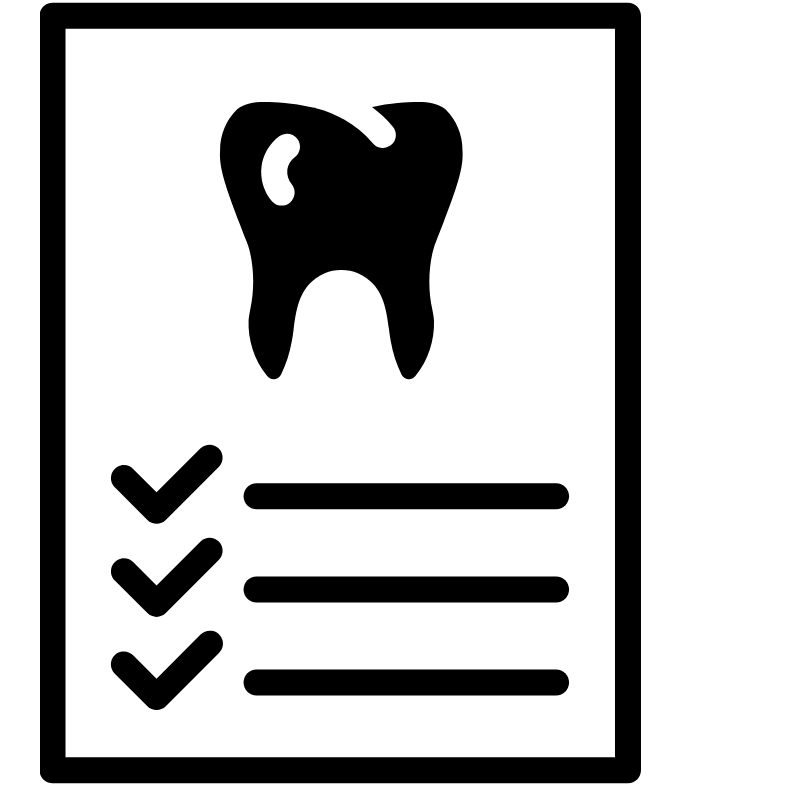
メインテナンス(Supportive Periodontal Therapy)
歯周病は完全に「治る」というよりも、「安定した状態を維持する」ことが重要な疾患です。そのため、治療後も定期的なメインテナンスが必要です。
メインテナンスの内容
- 歯周ポケット検査
- 専門的な歯の清掃(PMTC)
- 必要に応じてスケーリング
- セルフケアの再指導や修正
- 定期的なレントゲン検査(通常1年に1回程度)
- 必要に応じたCT検査(通常2〜3年に1回程度)
メインテナンスの間隔
歯周病のリスク(過去の進行度、全身疾患の有無、喫煙習慣など)に応じて、3〜6ヶ月に1回の頻度でメインテナンスを受けることをお勧めします。
患者さんご自身でできること
歯周病治療の成功は、歯科医院での治療だけでなく、患者さんご自身の日々のケアに大きく依存します。
日常のセルフケア
- 毎食後の丁寧な歯磨き(特に就寝前は重要)
- 歯間ブラシやフロスなどの補助的清掃用具の使用
- 必要に応じて洗口剤の使用
- 禁煙(喫煙は歯周病の大きなリスク因子)
- バランスの良い食事
- 十分な睡眠とストレス管理
定期検診の重要性
症状がなくても定期的に歯科医院を受診することで、問題の早期発見・早期対応が可能になります。「痛くなってから」では治療が複雑になることがあります。

まとめ
歯周病は静かに進行する病気ですが、早期発見と適切な治療、そして何よりも日々のセルフケアと定期的なメインテナンスによって、健康な歯を長く保つことができます。気になる症状があれば、早めに歯科医院へご相談ください。患者さん一人ひとりに合わせた治療計画を立て、サポートいたします。
